剛ちゃん
雑学や小話98
| 計算と物理 |
|
| |
| モーリス |
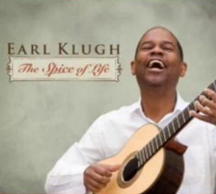 モーリス持てばスーパースターも夢じゃない♪ モーリス持てばスーパースターも夢じゃない♪学生の頃はフォークソングが流行っていた。 井上揚水、荒井由美、吉田拓郎、かぐや姫、小椋桂、など。 ギターを弾きながらハーモニカまで吹く器用な歌手もいた。 友達もギターを買い、アルペジオやスリ-フィンガーを練習していた。 どこかの市役所ではないが、何でもやる課の自分も挑戦した。 初めて様になった曲はスリーフィンガーで弾く「赤い花、白い花」だった。 さて、昭和50年前後のスナックではボックスの隅にギターを置いていた。 ギターが上手い奴の出番である。 ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |
| |
