新規サイト001のヘッダー
剛ちゃん
雑学や小話23
| 指の数 |
 自然は人に10本の指を与えた。 物をつかむのに便利な数なのだろう。 パソコンなどの電子機器は2進法でプログラムされている。 ICは電圧の有無、光ファイバーの中は光の点滅を0と1に読みかえている。 *進法とは*で桁上がりをする数の表記方法である。 10進法は0から数えて10で9から10に桁上がりする。 だから、数を記述する記号は0を含んで10個必要となる。 同様に、2進法は0から数えて2で1から10に桁上がりする。 さて、コンピューターのプログラムを計算する時、2進法を人が 計算すると0と1の羅列は間違いやすい。 そこで2進法の4桁をひとまとまりで変換できる16進数で表記している。 16進数は10進数でいう10をAで表わす、以下Fまでの記号を使っている。 |
| |
| 零の発見 |
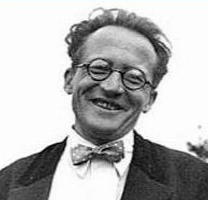 零はインドで発見された。 「数」としての零の概念を確立したのがインドである。 0はアラビアを経由してヨーロッパに伝わった。 インド数字の10や100を ローマ数字ではXやC、漢字では拾や百と書いていた。 ∴102=C2=百二 零は数として扱われなかった。 今、当たり前に0を計算しているが0が無かったらやりにくいだろうな。 ■0について ①1×0=0 なしか ∵ 一般論として1を自然数Aとする。 A×0=A×(0+0)=A×0+A×0 つまりA×0+A×0=A×0 ここでA×0=BとするとB+B=B BにBを足してBになる数は0しかない。 ∴B=A×0=0 つまりA×0=0 → 1×0=0 ②1÷0=(0で割る事は禁止) なしか ∵ 一般論として自然数ABCとして考える。 A÷B=C ⇔ C×B=A ここでB=0の場合を考える。 A÷0=C ⇔ C×0=A ところが①で説明したように C×0=0 A=1とすると C×0=1となりCがどんな数であってもC×0=Aは成立しない。 つまり自然数は0で割れない。 ③0÷0=不定 なしか ②のC×0=AはC×0=0となりCはどんな数でも成立する。 つまり、0÷0=Cはどんな数でもいい(不定)。 ■∞について 数学に無限大∞という記号がある。 ∞+1=∞ ∞-1=∞ ∞+∞=∞ これは明らかに右辺と左辺が異なるのに等号で結ばれている。 なしか ∵ ここでいう∞とは「無限大に発散する数列であって数ではない」と定義される。 ∞+1=∞の意味は「無限大に発散する数列に1に収束する数列を項毎に加えても 無限大に発散する」と主張しているだけ。 ①∞×0=不定 なしか 以下に3種類の数列を考える。 数列【1】 1,2,3,4.5,・・・・・・・・・・・・n・・・・・・・・・・・・→∞に発散 数列【2】 1,1/2,1/3,1/4,・・・・・・・・・1/n・・・・・・・・・・・→0に収束 数列【3】 1,1/4,1/9,1/16,・・・・・・・1/n*n・・・・・・・・・・・→0に収束 数列【1】×数列【2】=1×1,2×1/2,3×1/3,・・・=1,1,1,・・・・・・1に収束 ∴数列【1】×数列【2】=∞×0=1 数列【1】×数列【3】=1×1,2×1/4,3×1/9,・・=1,1/2,1/3,・・・・0に収束 ∴数列【1】×数列【2】=∞×0=0 →∞×0は様々な数列の組み合わせで1、0、-∞などになり「不定」となる。 ②∞-∞=不定 なしか この場合も 0、∞、-∞などになり、∞-∞はどんな数でもいい「不定」となる。 <考察 こんなことなら0を数として扱わなければいいのにとなるが、 0を使わないと計算がかえって複雑になる。 →数学は定義だらけの世界だった。 ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |
| |