新規サイト001のヘッダー
剛ちゃん
小話や雑学25
| 教える |
|
| |
| 藪の中 |
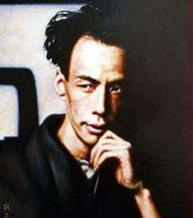 芥川龍之介は「羅生門」「杜子春」「トロッコ」「藪の中」「蜘蛛の糸」などを書いた作家。 「藪の中」は、藪の中で起きた殺人事件を7人の証言者が告白する内容である。 近年ではこの小説の題を借りて関係者の言い分が食い違ったり、証拠が不十分だったり、 証言者が少なかったりの理由で真相がはっきりしないことを表現する時に「藪の中」を使う。 さて、映画「羅生門」は1951年「ヴェネツィア国際映画祭グランプリ」を受賞した。 黒澤明監督や日本映画が世界に紹介されるきっかけとなった。 良い映画に違いない、ひとつ観てみるかと、レンタルビデオ屋さんで借りた。 しかし、訳の分からない退屈な映画だった。 題名は「羅生門」だが、筋書きはほぼ「藪の中」である。 「殺人事件を7人の証言者が告白する映画」と分かって見ないと何の事だか分からない。 「名物にうまいものなし」と同様に、「名作に必ずしも良いものなし」。 ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |
| |
