剛ちゃん
小話や雑学22
| プロパガンダ |
|
| |
| フーリエで解く |
 50歳を過ぎて、毎年人間ドックに行く。体のあちこちにガタがきている。 CTスキャンではベッドに横になり、洞窟のような機械に移動してゆく。 頭部の断層写真を撮り、異常なしで一安心。 さて、歯痛で歯科医院に行くと親知らずが顎の骨と癒着して抜歯できなかった。 数日後、総合病院の口腔外科で顎のCTスキャンを撮り、顎の骨を削ってやっと抜歯した。 <CTスキャンの原理 静止する体にX線を360度回転させながら投射する。 透過後に検出した画像は時間と共に変化するX線量のアナログ信号である。 これをフーリエ変換で信号処理をした後フーリエ逆変換すると断層写真が出来る。 フーリエ変換は今日の通信、医療などの科学分野に広く利用されている。 <実際の計算 人体の画像をf(X,Y)とし、ある角度θでのX線量の数値をR(θ,X)とする。 方程式は 微積分が式に入りこむと解が途端に難しくなる。 解を求めるには関数 f (X,Y)を三角関数の表現に置き換える。 この時にフーリエ級数やフーリエ変換を利用する。 ポイント:方程式が作れても簡単に解けない時にフーリエが活躍する。 詳細は以下を参照 http://www.enjoy.ne.jp/~k-ichikawa/Fourier13.html <フーリエ変換 フーリエは1811年に「全ての関数は三角関数の和で表わされる」と主張した。 関数(信号)そのものは複雑で解析しにくいので一旦スペクトルに変換する。 この根拠となっているのがフーリエ変換である。 微積分方程式の解を導く時、フーリエ変換で計算し易い三角関数に置き換える。 こねくり回した計算の最後にフーリエ逆変換して解を求める。 <複素フーリエ級数 フーリエ級数は複素数と自然対数の底eを使うことで、 三角関数から指数関数を含む複素フーリエ級数に発展した。 2回の微積分で元に戻る三角関数、さらに微積分で姿を変えないe のおかげで計算が容易になり、式も見やすくなった。 三角関数と指数関数を関連付けたオイラーのお陰である。→雑学74参照 <周期関数 周期関数はフーリエ級数の三角関数(周期2π)で表わされる。 それでは非周期関数はフーリエ変換が出来ないのか、と言うと実は出来る。 なんと周期を−∞から+∞の周期関数と見なして計算する。 そんなの有り?と思うが、ちゃんと計算ができるのだから数学は面白い。 <原理原則 「フーリエ級数を一旦認めれば計算が楽になり・・」とあるのに、 フーリエ関連の本を手に取ると微積分や行列などの超難解な式ばかり。 頑張って多くの計算をこなすことで実態が見えてくる、体力・若さ・情熱が必要である。 さて、フーリエ級数の数学的根拠や原理原則を知りたい。 何故フーリエが「全ての関数は三角関数の和で表わされる」との大胆な発想をしたか。 数学的根拠は慶応大学理工学部で講義している。 自宅で素敵な講義が受けれる時代は有難い。 慶応大学の講義 http://www.youtube.com/watch?v=0Uh5gwrTYF8&feature=relmfu FFT入門はフーリエの原理を解りやすく解説している、有難う! http://www.maroon.dti.ne.jp/koten-kairo/index.html ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |
| |
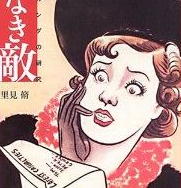 2013
2013